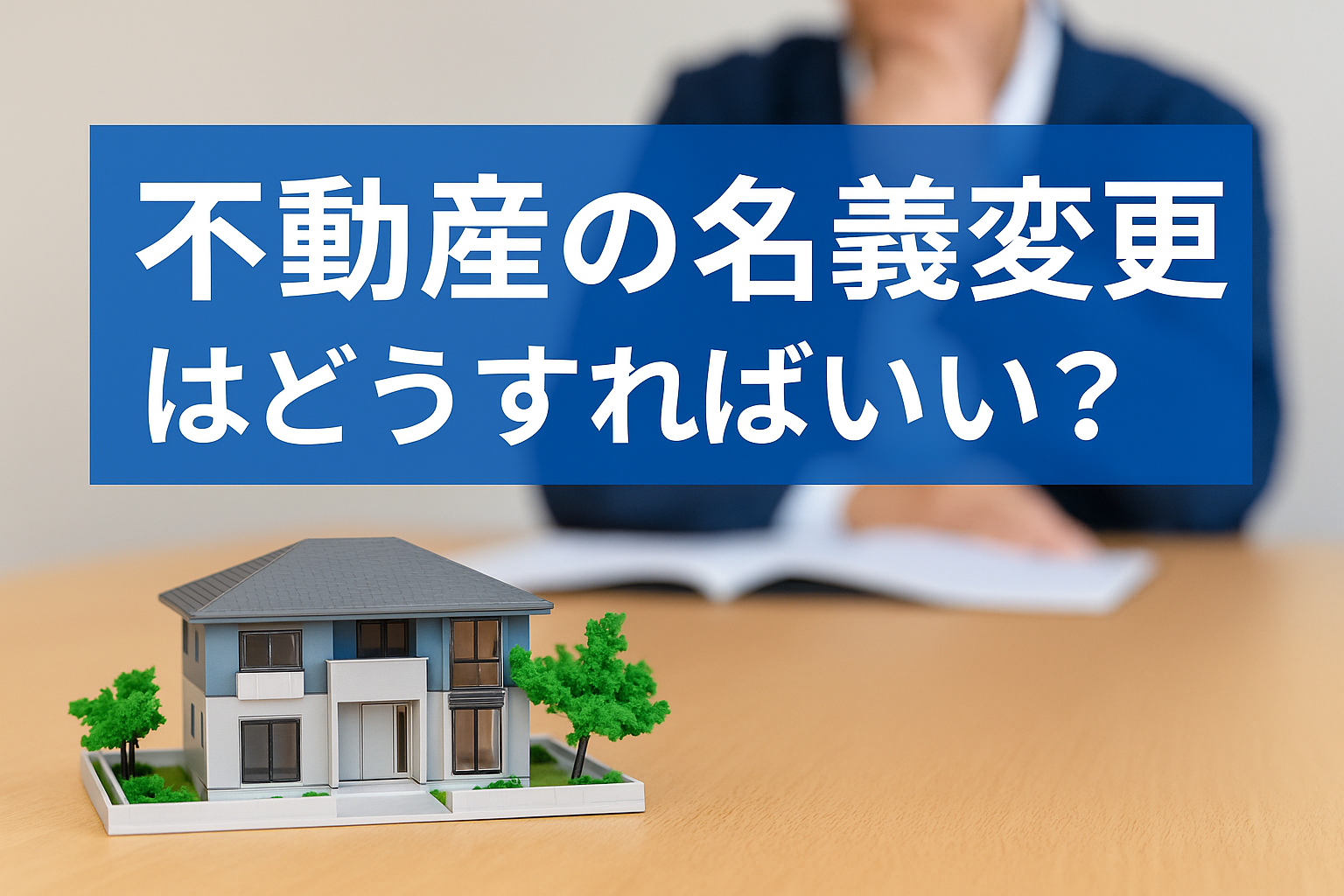相続で家や土地などの不動産の名義変更(相続登記)が必要になったとき、「何から始めればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。登記簿の名義が被相続人のままだと売却・担保・贈与などの手続きができず、放置すると相続人が増えて権利関係が複雑化することにもなります。さらに2024年から相続登記は義務化され、原則3年以内に申請しないと過料の対象になり得ます。本記事では、行政書士の視点で不動産 名義変更 相続の基本から実務のコツまで、やさしく整理します。
1. 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
売却・担保・贈与などの手続きが止まってしまう
登記簿の名義が亡くなった方のままだと、売買契約や抵当権の設定、持分の贈与などが進められません。金融機関や買主側の審査も通らず、実務上の支障が生じます。
放置で相続人が増え、合意形成が困難になる可能性がある
時間が経つと次の相続(数次相続)が発生し、配偶者や子のほか、兄弟姉妹・甥姪まで関係者が広がることも。決定に必要な同意者が増えるほど、話し合いは難しくなります。
相続登記の義務化に対応するため
2024年の制度改正により、相続登記は相続を知ってから3年以内が目安の義務に。正当な理由なく先延ばしにすると、10万円以下の過料となる可能性があります。
2. 名義変更(相続登記)の基本フロー
① 相続人の確定(戸籍の収集)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、法定相続人を確定します。(※)代襲相続の有無や婚姻・認知・養子縁組の記録も確認。誤った相続人で進めると登記がやり直しになるリスクがあるため、丁寧に進めましょう。
(※)代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)より先に相続人となるべき人が死亡、または相続権を失って いる場合に、その相続人の子や孫が代わりに遺産を相続する制度です。
② 遺言書の有無を確認
公正証書遺言があれば検認不要でスムーズに手続きへ。自筆証書遺言は原則、家庭裁判所の検認が必要です(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要)。
③ 遺産分割協議(遺言がない・一部のみのとき)
相続人全員で不動産の帰属を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。登記申請の根拠書類となるため、記載誤りや押印漏れがないようにする必要があります。
④ 申請書類の準備
相続登記申請書、被相続人の戸籍一式、相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書(または遺言書)、固定資産評価証明書などを用意します。
⑤ 法務局へ登記申請
不動産所在地を管轄する法務局へ提出します。審査完了後、登記簿の名義が相続人へ変更されます。オンライン申請や郵送も活用できます。但し、一般の方には手続きは複雑なため、専門家への相談をお勧めします。
3. 登記の方法は主に3パターン
1)遺言による相続登記
遺言書で不動産の承継者が特定されている場合、その指定に従って登記します。公正証書遺言であれば形式不備の心配が少なく実務上最も安全です。
2)遺産分割協議による相続登記
相続人全員の合意で承継者を決め、協議書を作成して登記。相続人間の公平感に配慮しつつ、将来の利用(居住・賃貸・売却)を見据えて分け方を検討しましょう。
3)法定相続による相続登記(持分の共有)
遺言や協議が整わない場合に法定相続分で共有登記する方法です。ただし将来の売却や管理の際に必要になる同意者が多くなり手続きが煩雑になりがちです。可能なら協議で単独相続にまとめることをお勧めします。
4. 必要書類・費用の目安
申請時に用意する主な書類
- 相続登記申請書
- 被相続人の戸籍(出生~死亡)、除籍・改製原戸籍
- 相続人の戸籍・住民票
- 遺言書(または遺産分割協議書)
- 固定資産評価証明書(登録免許税の算定に使用)
登録免許税とその他の費用
登録免許税は原則固定資産評価額の0.4%の金額が必要です。このほか戸籍・証明書の取得費、公証役場・専門家費用などがかかります。費用は物件数や相続人の数、遺言・協議の有無で増減します。
5. 相続登記でよくあるつまずきと対策
「戸籍が抜けていた/相続人が漏れていた」
出生から死亡まで連続した戸籍を必ず収集し、代襲相続や認知・養子縁組の有無も丁寧に確認しましょう。迷ったら専門家にチェックを依頼するのが安全です。
「協議がまとまらない」
評価の考え方や居住・売却の方針で意見が割れやすいのが不動産。中立的な第三者(行政書士・司法書士・税理士等)の助言で落としどころを探ると前進しやすくなります。調停へ進む前に冷静な整理を。
「登記を放置してしまった」
義務化により先延ばしはデメリットが増大します。次の相続が起きる前に早めの申請が重要です。相続人が海外・高齢などの場合は委任状やオンライン面談を組み合わせる等が効果的です。
6. 手続きを楽にする2つの小ワザ
法定相続情報一覧図を活用
法務局に法定相続情報一覧図を申出しておくと、戸籍一式の束を各機関へ毎回提出せずに済みます。銀行・証券・保険・税務など横断的に使え、紛失リスクの低減にも有効です。
評価・分割は税務の目線もセットで
不動産の分け方は相続税や譲渡所得税にも影響。小規模宅地の特例や将来売却時の税負担も見据えて、税理士と連携しつつ設計すると失敗が減ります。
7. 専門家に依頼するメリット
戸籍収集~協議書~申請まで一気通貫
相続登記は自力でも可能ですが、書類数が多く手戻りも起こりがち。行政書士に任せれば、必要書類の案内・収集、協議書の作成支援、申請書のチェックまでワンストップで進められます。
期限管理とトラブル予防
2024年の相続登記 義務化に伴い、期限や要件の見落としはリスクに直結します。プロの関与でスケジュール管理と証拠書類の整備を確実にし、紛争の芽を早期に摘み取ります。
8. まとめ:不動産の名義変更は「早め・正確・計画的」に
相続での不動産 名義変更は、放置すればするほど難しくなります。まずは相続人の確定と遺言・協議の整理、それから必要書類の準備と法務局への申請へ。2024年の相続登記 義務化にもしっかり対応し、将来の売却・活用を見据えた設計でスムーズに終えましょう。手続きに不安があるときは、どうぞお気軽に専門家へご相談ください。
クイズ
読み込み中…
…
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。