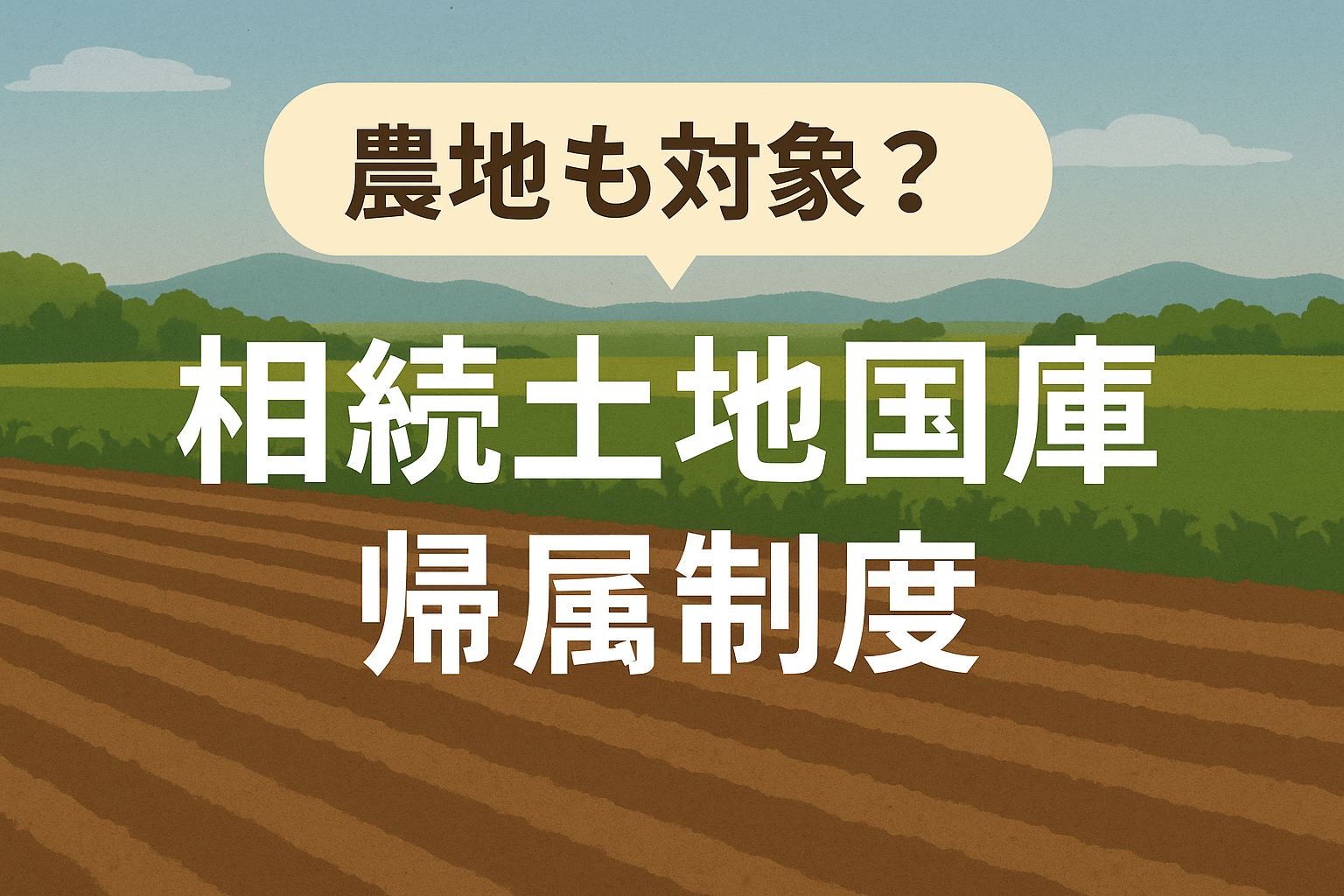「親から田畑や山を相続したけれど、もう使う予定がない」「遠方の土地の管理が重荷」──そんなお悩みを持つ方に、公的な新制度『相続土地国庫帰属制度』があります。
本記事は、法務省・政府広報など公的資料をもとに、農地は対象になるのか、どんな条件・費用・流れなのかを、行政書士の視点でやさしく解説します。
1. 制度の概要:相続土地国庫帰属制度とは
制度の目的と背景
令和5年(2023年)4月に始まった制度で、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる仕組みです。所有者不明土地の増加や、管理困難な土地の放置による社会問題(防災・防犯・環境)に対応するために創設されました。
運用と相談窓口
受付・審査は法務局(地方法務局)が担当します。申請の前に事前相談(予約制)が用意されており、登記事項証明書や地図・写真などを持参して可否の目安を確認できます。
2. 農地も対象になる?:対象範囲と基本条件
結論:条件次第で農地も申請可
宅地だけでなく、農地・山林なども対象になり得ます。ただし、農地には特有の事情(農用地区域、水利・農道、土地改良区との関係等)があり、通常より審査が慎重になるのが一般的です。
申請時に満たすべき主な条件(公的基準の要旨)
- 建物・工作物がないこと(残置物・埋設物にも注意)
- 境界が明確で争いがないこと
- 他人の通行・使用が予定されていないこと(水路・農道は要注意)
- 土壌汚染・危険がないこと
- 通常管理に過大な費用を要しないこと(崖地等は不利)
※農地は現況(実際の使われ方)を重視されます。登記上の地目と現況が異なる場合は、現況確認の資料(写真・証明)が役立ちます。
3. 公的資料で見る制度の現状
申請の傾向と審査ポイント
制度開始後、各地で申請が進んでいますが、承認率は一律ではなく、不承認理由としては「工作物の存在」「境界不明」「通行・水利の支障」などが目立ちます。農地は関係法令や地域実情の確認が必要なぶん、時間がかかる傾向があります。
4. 手続きの流れ:法務局でのステップ
1. 事前相談(予約制)
所在地を管轄する地方法務局で、制度の対象になり得るかの目安を確認します。登記事項証明書、地図・公図、現況写真、必要に応じて境界や水利の資料を準備しましょう。
2. 承認申請の提出
法務省様式に沿って申請書を作成し、必要書類を添付します。農地の場合、農業委員会の証明や土地改良区との関係資料を求められることがあります。
3. 審査・現地調査
法務局が書類審査のほか、現地確認を行います。境界標・地物・接道・水路など、管理や処分に支障がないかを確認します。
4. 承認・負担金の納付・国庫帰属
承認通知後、指定期限内に負担金を納付すると、所有権が国に移ります。これで管理負担から解放されます。
5. 費用と算定の考え方
審査手数料と負担金の目安
- 審査手数料:1筆あたり14,000円(全国一律)
- 負担金:原則1筆あたり20万円
ただし、森林や広大な農地など維持管理に特別の費用が見込まれる場合は、面積比例で加算されることがあります。都市計画区域・用途地域・地域特性によっても算定が異なる可能性があるため、事前相談で見込みを確認しましょう。
6. 農地で特に注意したいポイント
農用地区域(青地)・水利・農道
農業振興地域の農用地区域にある農地は、将来の農業利用を前提としているため、国庫帰属のハードルが高くなりがちです。農道・水路が絡む場合は、第三者の利用や管理の手当が必要になり、不承認の一因となることがあります。
共有名義の土地
共有地は共有者全員の同意と連名申請が必要です。1人でも反対すると申請できません。相続で共有化している土地は、早めに話し合いの場を設けましょう。
残置物・埋設物・境界の不明確
納屋・基礎・擁壁・井戸・廃材・地中埋設物などは不承認の典型です。境界が曖昧なときは、測量や合意書面の用意が近道です。
7. メリットと限界(使う前に知っておく)
メリット
- 「売れない・使えない」土地を公的に手放せる
- 相続放棄をしなくても対象の土地だけ処理できる
- 将来の管理負担・トラブル不安を軽減できる
限界・注意点
- 誰の土地でも承認されるわけではない(不承認要件あり)
- 審査期間がかかる(数か月~案件により1年以上)
- 最小でも20万円+手数料程度の費用負担が必要
申請後でも、実地調査や追加資料の結果、判断が変わることがあります。最初に「通りやすい設計」で臨むことが重要です。
8. 進め方のコツ
1. 書類を少しずつ集める
登記事項証明書、公図・地図、固定資産税の課税明細、現況写真、相続関係(戸籍)など、まずは手に入る資料から。農地なら農業委員会や土地改良区の書類も役立ちます。
2. 相談は「早め・予約制」で
法務局の相談窓口は予約制です。概要を確認してから準備することで、無駄な手戻りを減らせます。
3. 専門家をハブに
農地は関係者・法令が多く、書類づくりも骨が折れます。行政書士に依頼すれば、資料の整備・関係機関連携・申請実務をスムーズに進められます。
9. まとめ:農地も対象になり得る。まずは“可否の目安”を
相続土地国庫帰属制度は、使わない土地を国に引き取ってもらえる新しい選択肢です。農地も条件を満たせば対象ですが、地域事情や関係法令の確認が不可欠。まずは法務局の事前相談で可否の目安をつかみ、必要に応じて専門家の力を借りましょう。
クイズ
読み込み中…
…
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。