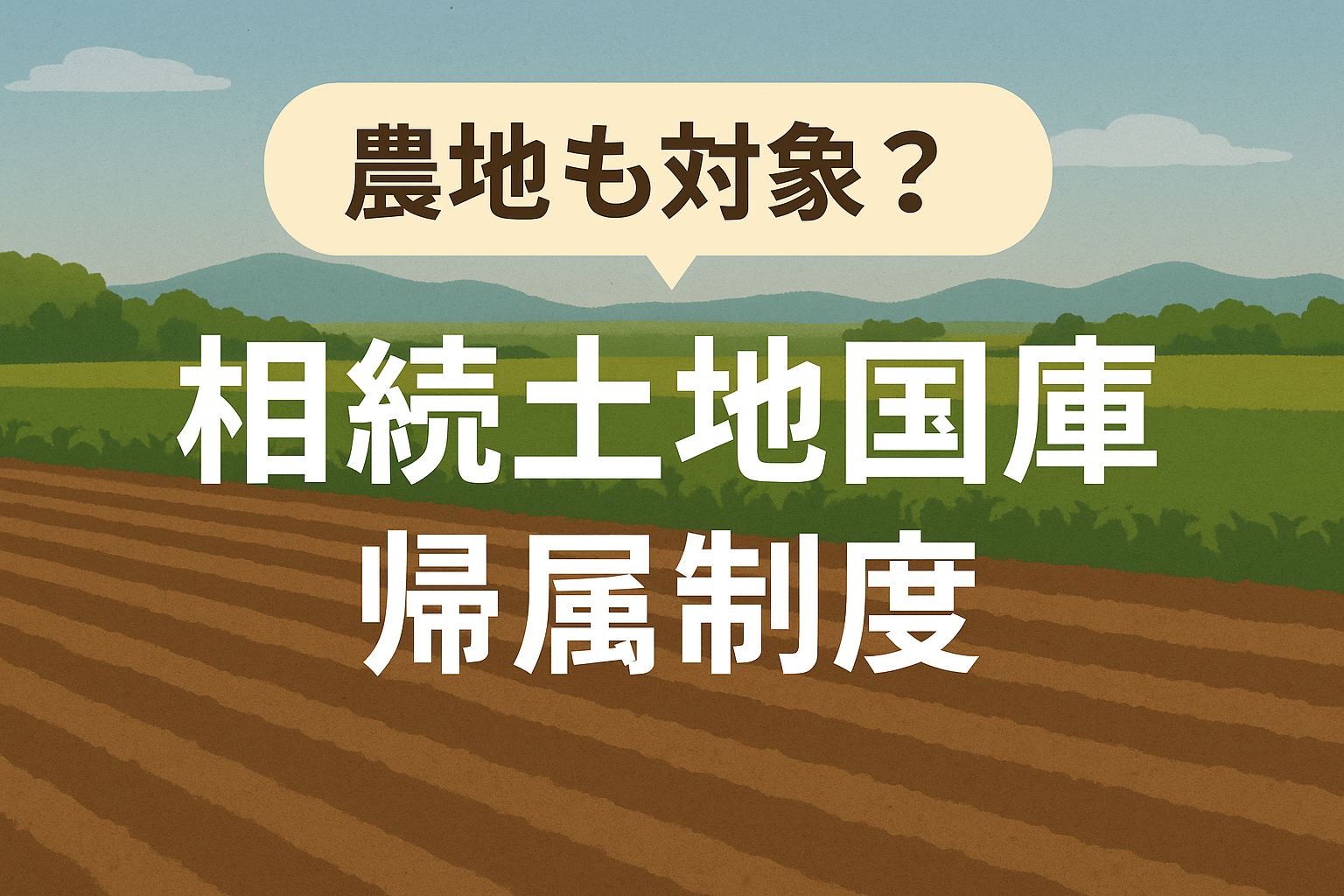「相続の手続きを始めたいのに、兄弟のひとりと何年も連絡が取れない」「親戚が海外に移住して所在が分からない」。
行政書士としてご相談を受ける中で、この悩みは決して珍しくありません。
本記事は、分かりやすく今から何をすれば手続きが前に進むのかをやさしく解説します。
なぜ「行方不明の相続人」がいると相続が止まるのか?
相続は“全員参加・全員合意”が原則
相続では、遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要です。ひとりでも欠けると協議書は有効にならず、銀行の解約や不動産の名義変更も進みません。たとえ音信不通でも、その人の相続権は自動的に消えないからです。
「いないもの」として先に進めるのは危険
話し合いを急ぐあまり、所在不明者を除いて勝手に分けてしまうと、後日無効とされ、やり直しになる恐れがあります。焦らず、法律の仕組みを使って一歩ずつ前へ進めましょう。
第一歩は“所在確認”。ここを丁寧にやると後がラク
役所・郵便・周辺の手がかりを総動員
- 住民票・戸籍の附票で住所履歴を追う(市区町村)
- 転居届・転送記録の有無を確認(郵便局)
- 親族・友人・勤務先・大家などに聞き取り
- 電話・メール・SNS・手紙(書留/内容証明)でコンタクトを試みる
結果が出なくてもOK。「いつ・何を・どう試したか」をメモや控えで残しましょう。後の裁判所手続きで「やるべき努力を尽くした」ことの証拠になります。
小さな実例:書留を最終住所に送ったところ「転居先不明で返戻」。この封筒自体が立派な証拠に。さらに親族からの聞き取りメモを添えると説得力が増します。
見つからないときの切り札「不在者財産管理人」
どんな制度?何ができる?
不在者財産管理人は、長期間所在不明の人(不在者)に代わり、財産を守りつつ必要な手続きを進める家庭裁判所選任の代理人です。選任後、裁判所の許可を得れば遺産分割協議に参加し、署名・押印が可能。ここから一気に実務が動き出します。
申立ての流れ
- 申立先を確認(不在者の最後の住所地の家庭裁判所)
場所の確認と電話予約。 - 必要書類を集める:申立書、戸籍・住民票除票、申立人の戸籍、財産目録、所在確認の記録など
収集と整理に時間がかかる。早めの着手が安心。 - 審査・選任:弁護士や司法書士が選任されるのが一般的(事情により親族が選ばれることも)
裁判所が適任者を決定。
選任後の実務フロー
- 管理人が遺産の内容・分け方案を把握
- 家庭裁判所へ分割協議の許可を申立て
- 許可後、他の相続人と協議書を作成し、管理人が署名・押印
- それをもとに、預貯金解約・名義変更・相続登記へ進む
ポイント:管理人は不在者の利益を守る義務があります。偏りの大きい分け方や根拠の薄い評価は、許可が出ないことも。妥当性の高い説明資料を揃える必要があります。
それでも長期不明なら「失踪宣告」を検討
普通失踪と特別失踪
- 普通失踪:7年以上生死不明のとき
- 特別失踪:災害・事故など生命の危険後、1年以上生死不明のとき
裁判所が認めると、法律上は死亡したものとみなされるため、通常の相続として手続きが可能に。ただし後日生存が判明した場合の財産返還など、法的整理が必要になるため、慎重な判断が必要です。
実務でつまずきやすいポイントと回避策
1. 「探した記録」が弱い
書留・内容証明の控え、不達票、返戻封筒、聞き取りメモなど、客観資料を積み上げましょう。結果が出なくても、努力の履歴が価値となります。
2. 行方不明者を外して協議してしまう
のちに無効や紛争の火種に。管理人選任→裁判所許可→協議という正規ルートを踏むのが結局いちばん早い近道です。
3. 不動産の相続登記(申請義務)を失念
不動産がある場合、相続登記は原則3年以内に申請が必要(正当理由なく怠ると過料の可能性)。長期化が見込まれるなら、中間対応(例:相続人申告登記)でリスクを抑えましょう。
ワンポイント:評価や分け方の「納得感」を数値化
物件の固定資産税評価、残高証明、時価の根拠など、数字で裏づけると裁判所の許可が得られやすく、家族間の納得感も高まります。
こんなケースでも前に進めます
住民票上の住所はあるが反応がない
内容証明で協議参加を正式要請。返戻や不達も証拠化。応答がなければ調停申立てで裁判所関与へ。必要に応じて不在者財産管理人を申立てます。
住所履歴が途絶え、手がかりゼロ
附票・除票の探索、親族・知人への丹念な聞き取りを。記録を整えた上で不在者財産管理人へ。長期なら失踪宣告も視野に入れます。
海外在住で連絡はつくが手続きが進まない
在外公館(大使館・領事館)の署名証明・在留証明を活用。郵送往復や翻訳の手間があるため、ゆとりあるスケジュールを組みましょう。
専門家に相談するメリット(行政書士ができること)
資料の抜け漏れを防ぎ、段取りを作る
- 戸籍・住民票・附票類の収集/相続関係説明図の作成
- 財産目録の整備(不動産・預貯金・有価証券・デジタル資産)
- 所在確認の経緯を裁判所に伝わる形で書面化
家庭裁判所・他士業と連携し、最短ルートへ
- 不在者財産管理人選任申立ての書類作成補助
- 管理人(弁護士・司法書士)との実務連携、進行管理
- 遺産分割協議書の作成、公証役場・法務局・金融機関対応の段取り
家族間で感情がぶつかりやすい場面でも、第三者が入ることで話し合いが落ち着きます。やり取りを記録し、後から説明できる形に整えるのも大切な役割です。
まとめ:立ち止まらない。記録・制度・専門家で前へ
行方不明の相続人がいても、所在確認の記録を積み上げ、不在者財産管理人を活用し、必要に応じて失踪宣告を検討すれば、相続は法的に前へ進められます。焦らず、正しい段取りを踏みましょう。
クイズ
読み込み中…
…
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。