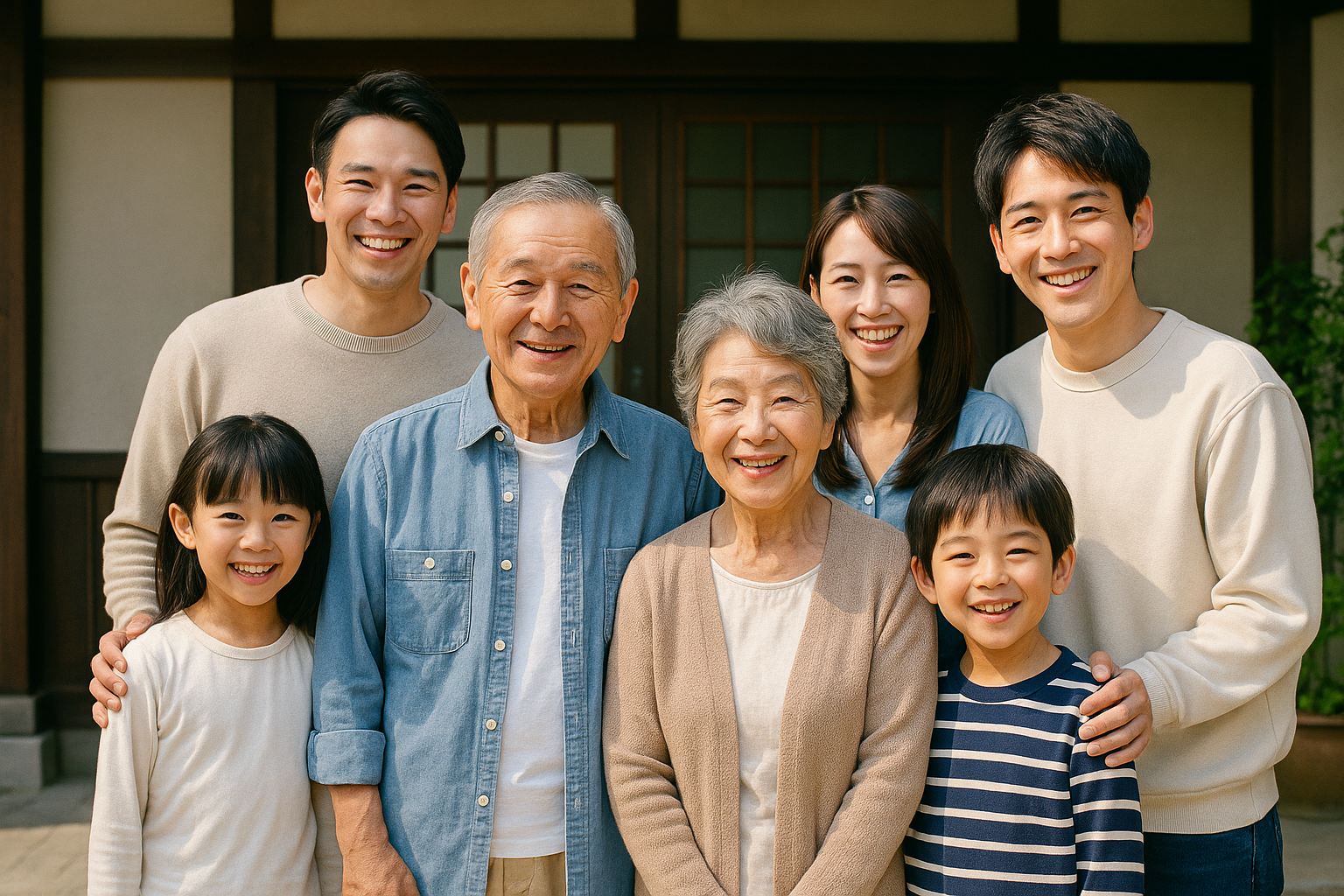1. はじめに
大切な家族や身近な人が亡くなられたとき、深い悲しみの中でも避けて通れないのが「相続の手続き」です。財産をどう分けるのか、不動産や預金の名義をどうするのか、やるべきことは思っている以上に多岐にわたります。いざ向き合ってみると「何から手をつけていいのか分からない」「間違えたら後でトラブルになるのでは」と戸惑う方も少なくありません。
相続は家族の感情と法律上のルールが複雑に絡み合うものです。だからこそ、冷静に計画的に進めることが何より大切です。今回は、行政書士の視点から「相続手続きはまず何から始めればいいのか」について、できるだけ分かりやすくご説明します。
2. 相続手続きの第一歩は「相続人の確定」と「財産の把握」
相続の手続きは大きく分けると、①相続人を確定すること、②財産を把握すること、③遺言書の確認、④遺産分割協議、⑤各種名義変更・税務申告、という流れになります。
その中でも土台となるのが「相続人の確定」と「相続財産の把握」です。ここをきちんと行わないと、その後の手続きが進まず、最悪の場合は相続自体がやり直しになることもあります。
3. 相続人の確定
まず取り組むべきは「誰が相続人になるのか」を明確にすることです。これは単に「家族だから」という感覚だけで判断できるものではなく、法律で定められたルールに基づいて決まります。
具体的には、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を一つ残らず収集し、相続関係を確認します。例えば、亡くなった方に認知した子どもがいたり、養子縁組をしていたりする場合、その人たちも相続人になるケースがあります。逆に、兄弟姉妹は子どもがいる場合には相続人にはなりません。このように「思っていた人が相続人ではなかった」「知らない相続人がいた」と後から発覚することも珍しくないのです。
戸籍の収集は、市区町村役場で戸籍謄本を請求することで可能ですが、本籍地が何度も移っていると複数の役所に問い合わせる必要があります。戸籍の形式も時代によって異なるため、読み解くのに専門知識が必要になる場合もあります。行政書士は戸籍の収集や相続関係説明図の作成をお手伝いできるので、不安があれば依頼されると安心です。
4. 相続財産の把握
相続人が分かったら、次は「何を相続するのか」を確認します。相続財産は、預貯金、不動産、有価証券、車両、生命保険などのプラスの財産に加え、借金やローン、未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。
財産調査を怠ると「知らなかった借金が後から見つかった」という事態になりかねません。そのため、通帳、不動産登記事項証明書、保険証券、借入契約書などを整理し、できるだけ正確に財産の全体像を把握することが重要です。
また、財産の内容次第では「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢も検討しなければなりません。これらの手続きは原則として被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行う必要があるため、調査は早めに着手することが求められます。
5. 遺言書の確認と遺産分割協議
相続人と財産が確定したら、遺言書の有無を確認します。公正証書遺言がある場合は、公証役場に原本が保管されていますので、すぐに手続きを進められます。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ効力を持ちません。遺言書は原則として法定相続分よりも優先されますので、まず内容を確認しましょう。
遺言書がない場合や、遺言書があっても一部の財産が対象外となっている場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。この協議では、誰がどの財産を取得するかを話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この書類がなければ、不動産の名義変更や銀行口座の解約ができません。協議が難航する場合には、家庭裁判所で調停を行う方法もあります。
6. まとめ
相続手続きは、感情面の負担と法的な複雑さが重なり、「何から手をつければいいのか分からない」という声が非常に多い分野です。しかし、最初の一歩として「相続人の確定」と「財産の把握」を丁寧に行うことで、全体の流れが見えやすくなり、その後の遺言書確認や遺産分割協議もスムーズに進めることができます。
行政書士は、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きの初期段階から専門的にサポートすることができます。ご自身で進めるのが不安な場合や、相続人の数が多く複雑な場合は、早めに専門家へご相談ください。正しい手順を踏むことで、相続を「安心して進められる手続き」に変えることができます。
クイズ
相続クイズ
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。