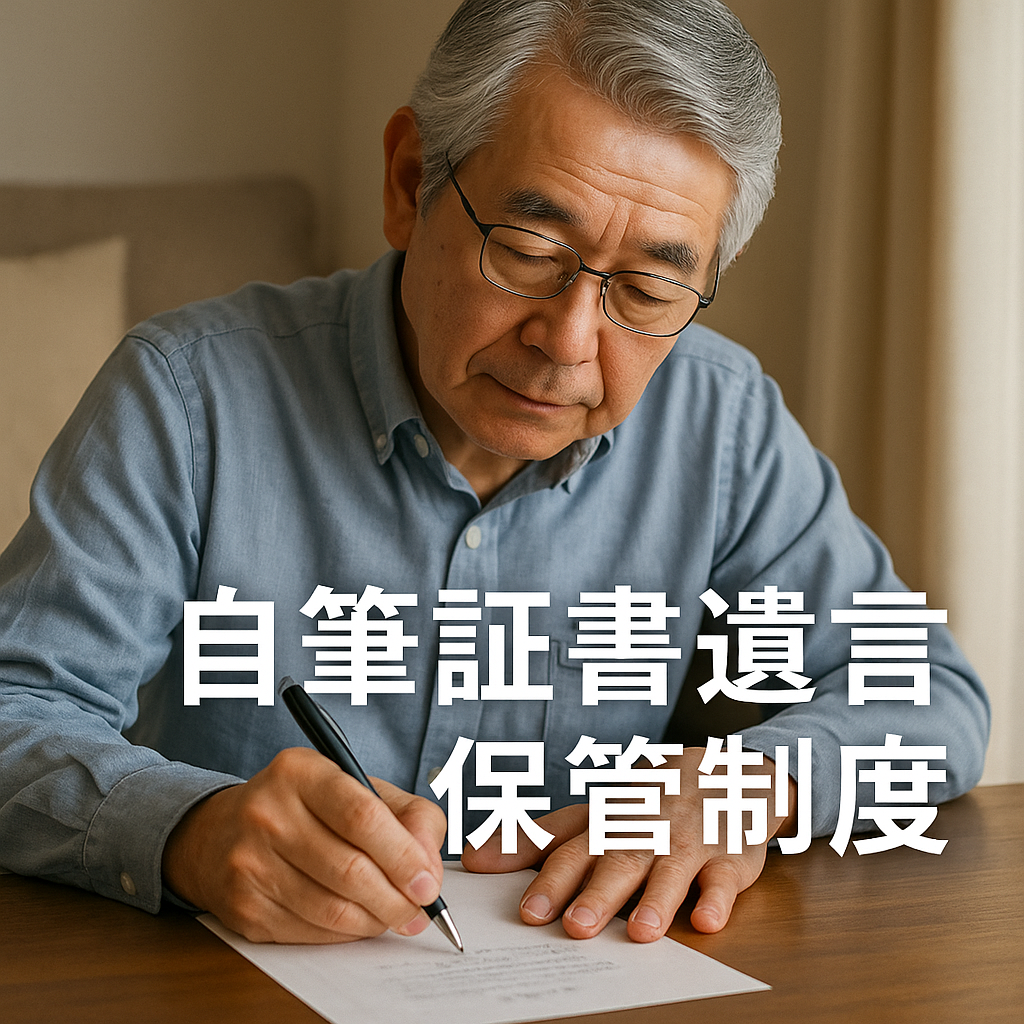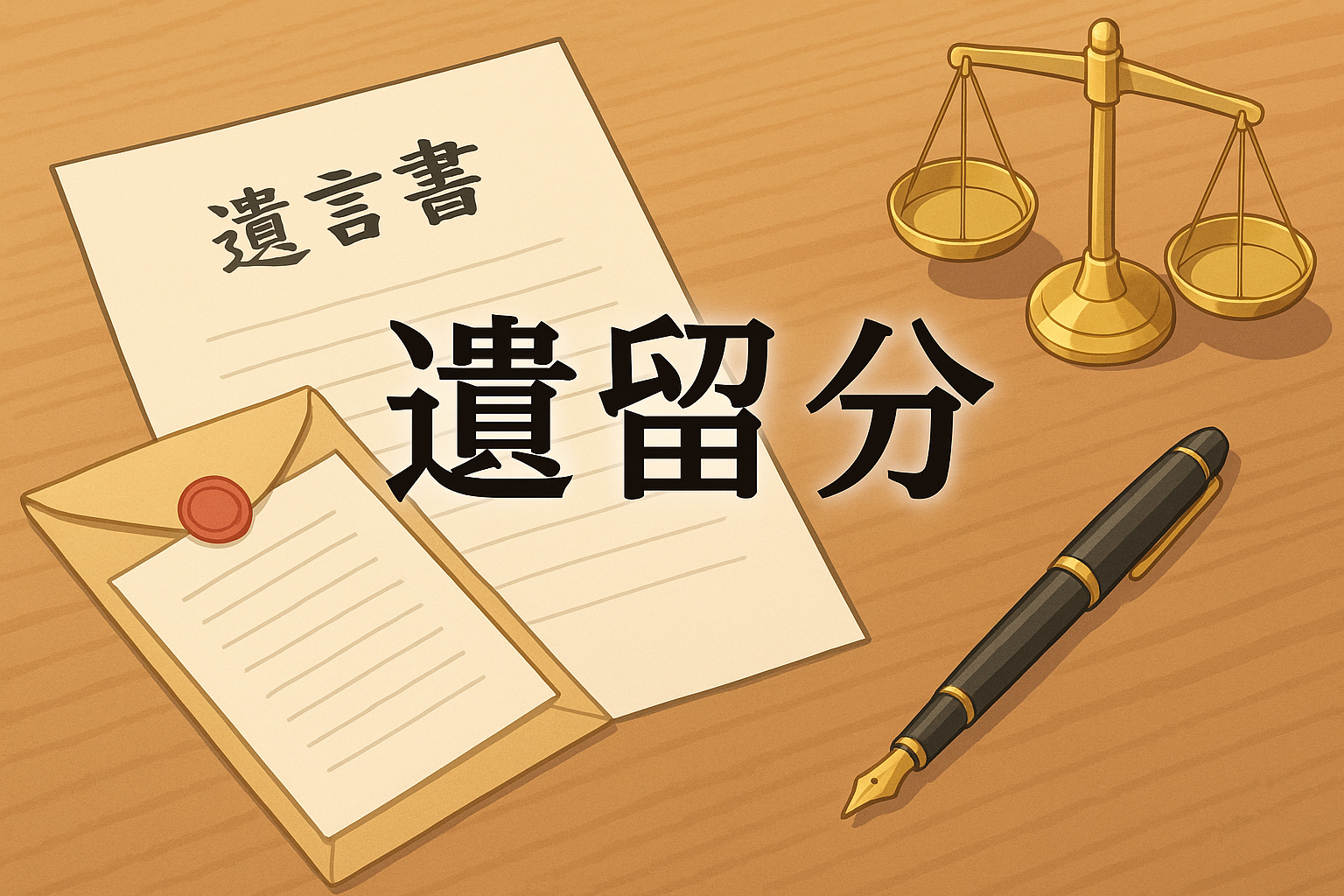「遺言書を自分で書きたいけれど、保管が不安…」そんな声をよくお聞きします。 令和になって設けられた “自筆自筆証書遺言保管制度” は、その不安を少し軽くしてくれる制度です。 ただし、万能ではありません。本記事では、制度の利用手順、得られるメリット、注意すべきリスク、さらには「どんな人に向いているか」を、行政書士の視点からご紹介します。
1. 自筆証書遺言保管制度とは何か?まずは制度の仕組みを押さえよう
これまでの自筆証書遺言は、自宅で保管したり、封をしておいて開封前に家庭裁判所で検認を受けたりと、家族が発見できないリスクや紛失・改ざんの恐れがありました。 この制度は、法務局(遺言保管所)が遺言書を預かり、厳重に保管し、必要時に取り出せるようにする公的な仕組みです。
具体的には、遺言者本人が法務局に出向き、自筆の遺言書を保管所に預け、保管証が交付されます。 保管中は遺言が改ざんされる可能性を減らし(ほぼゼロ)、遺言者死亡後には家庭裁判所の検認が不要になる点が大きな特徴です。
制度の導入背景
相続に関するトラブル・遺言書の紛失や偽造による争いを減らすため、国がより安全な遺言制度を目指して整備したものです。法務省でも制度概要・Q&Aが公開されています。
2. 制度を利用するまでの流れ:誰でもできるステップを丁寧に
保管を始めるには、以下のような流れになります。
1. 遺言書の準備
遺言を書く際には、自筆で全文を記す必要があります(遺言者が手書き)。日付・署名・捺印も忘れてはいけません。法務局では内容に関与しないため、形式の正確性が重要です。
2. 申請予約と持参資料の準備
最寄りの法務局遺言保管所で予約を取り、以下のような書類を準備します: → 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) → 保管を希望する自筆遺言書 → 登記済権利証・戸籍抄本など必要に応じて
3. 遺言書の保管申請
法務局に赴き、遺言書を預ける手続きをします。 遺言保管所で遺言書を確認し、封印・保管されます。預けた遺言には「保管証」が交付され、これが預けた証拠になります。
4. 死後・発見時の手続き
遺言者が亡くなった場合、遺言を保管していた法務局に請求ができます。 請求者は、遺言書の閲覧・写し交付・原本の交付を受けられます。家庭裁判所での検認が不要なのがこの制度の大きなメリットです。
3. この制度を使うメリット:遺言を“守る力”を得られる
まず、”改ざん・紛失・偽造リスクを減らせる“点が最大の利点です。法務局の公的保管なら、遺言が安全に保存されます。 次に、遺言者が亡くなった際に”検認を受ける手間が省ける“点。通常、自筆遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、この制度を使えば不要です。これにより、相続手続きがスムーズになります。
また、保管証を交付されることで、遺言を“預けた事実”が明らかになります。これにより、遺族が「遺言があるかもしれない」と探し回る手間を減らせます。
4. 注意したいリスクや制限も把握しておこう
ただし、この制度は万能ではありません。いくつかのリスク・制限があることを理解しておくことが肝心です。
法務局は中身をチェックしない
保管所は遺言内容の妥当性や法的有効性を審査しません。形式不備(署名がない、日付不明など)は預けられない可能性があります。
保管手数料やコストがかかる
保管料や技術的な手数料が発生します。少額ながら費用がかかるため、どの遺言書を預けるかを選ぶ必要があります。
遺言の変更や取り戻しには手続きが必要
一度保管した遺言を取り下げたり書き直したりするには、追加手続きが必要です。手軽に頻繁に書き換える用途には向かないこともあります。
誰にも見せたくない“思い”は書きづらい
感情的なメッセージや家族への手紙のような内容は、遺言書よりノート形式の記録(エンディングノートなど)に適しています。
5. 制度を使うべき人・向かない人を考えてみよう
この制度が特に向いているのは、以下のような方々です:
・「自筆遺言を用意したいが、自宅保存が不安」
・「遺言が見つからず混乱することを避けたい」
・「法的な部分は専門家に任せながら、中身や希望を自分で書き残したい」
逆に、制度を使わなくても良い可能性がある方もいます。例えば、すでに公正証書遺言を作っている方、複雑な財産分割が予想される方、遺言を頻繁に書き直す方などです。
6. 長く使えるノウハウ:活用のコツと注意点
制度を活かすためには、以下の点を意識しておきましょう。まず、遺言書を清書する際は形式に注意し、日付・署名・捺印を明確に。そして、遺言を書いたらすぐ保管制度を使うことで、紛失リスクを下げられます。
また、書き直す可能性がある方は、「以前の遺言を破棄する旨を記す」などの備えを入れておくと後日もスムーズです。さらに、家族には保管したこと・保管機関を伝えておくことが望ましいでしょう。
7. まとめ:法的な支えを持つ遺言+安全な保管が安心につながる
自筆証書遺言保管制度は、「遺言を書きたいけど不安がある」方にとって非常に有効な選択肢です。ただし、形式や手続きには注意が必要で、すべての人に万能というわけではありません。 遺言書とノート形式の記録(エンディングノートなど)を併用し、思いを法律と記録の両面で残すことが、あなたと残されたご家族の安心につながります。
もし「この遺言書を保管制度で預けられるか」「書き方のチェックが欲しい」といったご相談があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。行政書士として、あなたの思いを正しく残すお手伝いをいたします。
クイズ
読み込み中…
…
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。