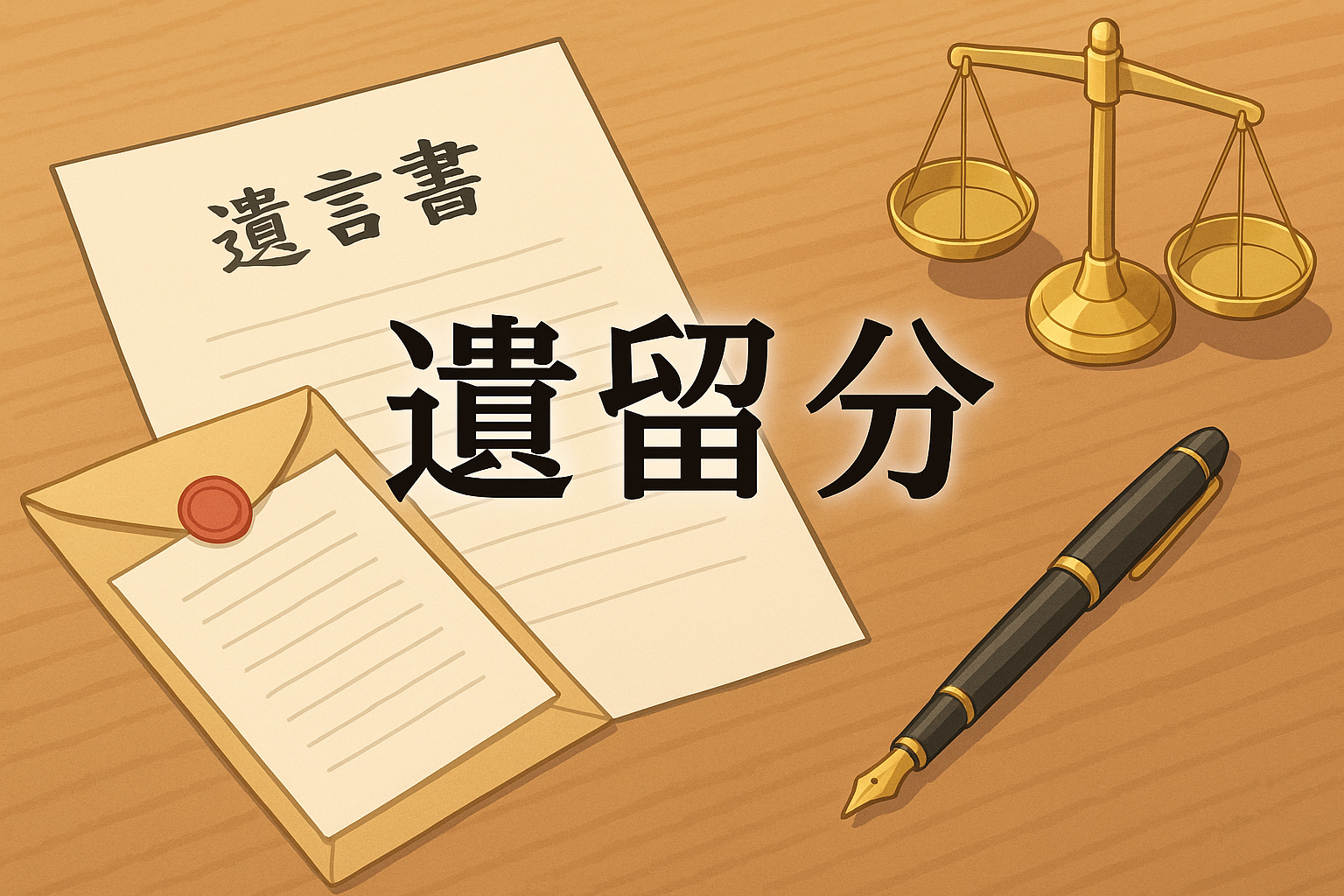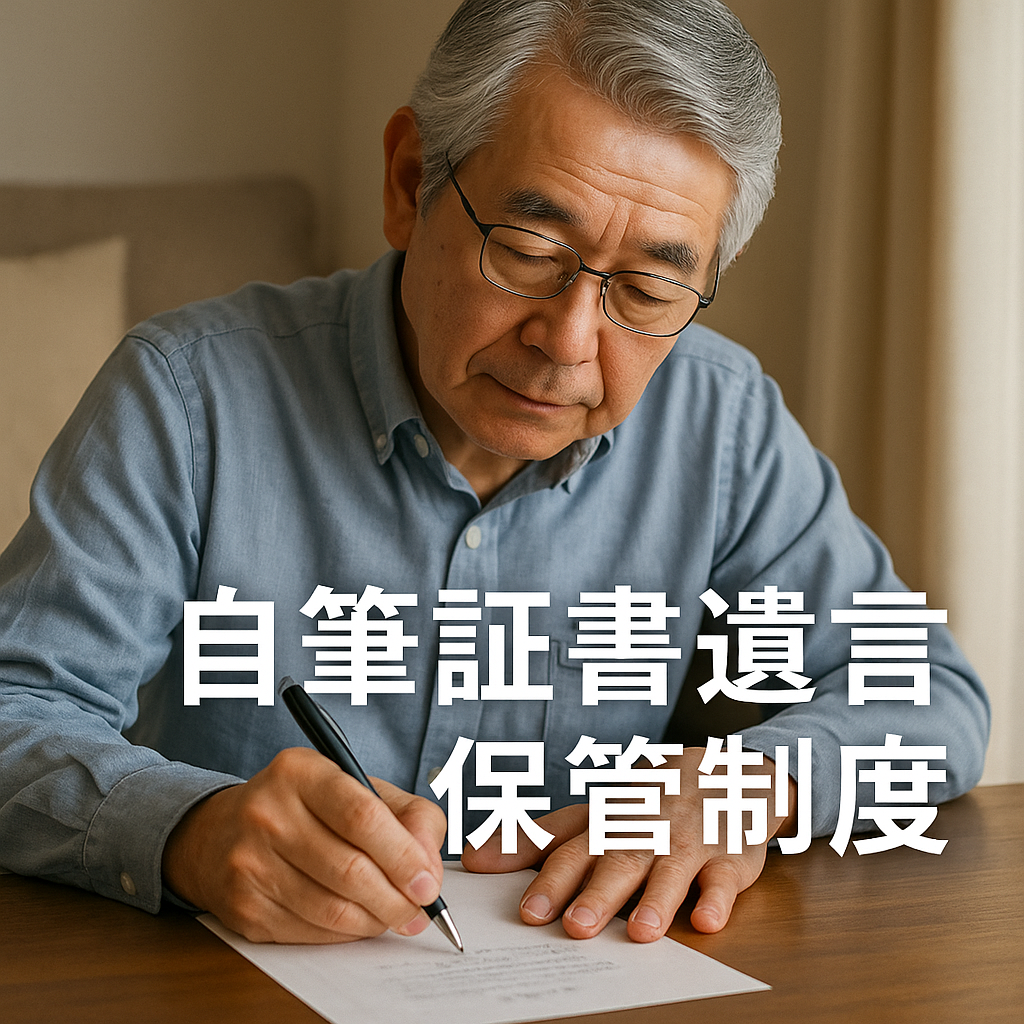「遺言書に“全財産を長男に相続させる”と書けば、それで決まりだと思っていた」──実際、こうしたご相談はとても多いものです。 ところが現実には、遺言書の内容があっても、法律で守られた取り分「遺留分(いりゅうぶん)」があり、すべての財産を一人に渡すことは原則としてできません。 本記事では、遺留分の基本的な考え方から、トラブルを避ける工夫まで、行政書士の立場からわかりやすくお話しします。
1. そもそも「遺留分」とは?
遺留分とは、相続人の中でも特定の人に保証されている“最低限の取り分”のことです。 簡単に言えば、遺言で「すべて長男へ」と書かれていても、他の相続人(配偶者や子ども)には、法律で一定割合の権利が残されている、という仕組みです。
この制度の目的は、残された家族の生活を守ること。 たとえば専業主婦だった配偶者が、急に遺言で何も受け取れなくなったら生活に困ってしまいますよね。 そうした不公平を防ぐために、民法が遺留分というルールを設けています。
2. 遺留分がもらえるのは誰?割合はどのくらい?
遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども(または代襲相続人)・直系尊属(父母など)のみです。 兄弟姉妹には遺留分はありません。 具体的な割合は次のとおりです。
1. 配偶者と子どもがいる場合
全体の相続財産のうち、遺留分全体は1/2。その1/2をさらに家族で分け合う形です。 たとえば妻と子ども2人の場合、妻は1/4、子ども2人で残り1/4を分け合う計算になります。
2. 配偶者のみが相続人の場合
遺留分は全体の1/2です。 「全財産を他人に遺贈する」と書かれていても、配偶者は半分を取り戻すことができます。
3. 子どもだけが相続人の場合
この場合も全体の1/2が遺留分として守られます。 子どもが複数いるときは、その1/2を人数で分け合います。
※親のみが相続人のときは、全体の1/3が遺留分です。
3. 遺留分を侵害されたらどうする?請求の流れを知っておこう
もし、自分の遺留分が遺言によって侵害されていた場合、相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。 これは、遺言や贈与で多く財産をもらった人に対して、「自分の取り分を返してほしい」と請求する手続きです。
いつまでに請求すればいい?
遺留分の請求には期限があります。 「相続の開始と侵害を知った時から1年以内」または「相続開始から10年」が経つと、請求する権利がなくなります。 感情的な整理がつかず後回しにしているうちに、気づいたら期限切れ……というケースも少なくありません。
請求の方法は?
まずは話し合い(任意の交渉)から始めるのが一般的です。 それでもまとまらない場合は、家庭裁判所に「調停」や「訴訟」を申し立てます。 書面や証拠をそろえる手続きになるため、専門家のサポートを受けた方がスムーズです。
4. よくあるトラブルと注意点
遺留分をめぐるトラブルは、思っている以上に多いものです。 特に多いのが、感情的な行き違い。 「兄が全部もらうなんて納得できない」「父の意思を無視するのか」といった争いが、家族関係を壊してしまうこともあります。
また、遺留分を計算する際の「財産の評価」もよく揉めます。 不動産の時価をどうみるか、死亡前に贈与した財産を含めるか──。 この辺りは専門的な判断が必要です。
そして、もう一つの注意点は請求できるのは金銭であること。 以前は「物そのものを取り戻す」請求ができましたが、現在はお金で清算する方式です。 そのため、現金をすぐ用意できない相手との交渉は長引くこともあります。
5. トラブルを防ぐために今できること
「争いを避けたい」と思うなら、生前からの準備が大切です。 遺言書を書くときに、遺留分を考慮した内容にしておくのが一番の予防策。 行政書士など専門家に相談すれば、法的に有効かつ円満な形で遺言を残すことができます。
また、生前贈与の活用も一つの方法です。 ただし、遺留分の計算に「生前贈与分」が含まれるケースもあるため、贈与の時期や金額には注意が必要です。
もし「すでに家族で話がこじれている」「遺言内容に納得がいかない」という場合は、早めに専門家へ。 感情的に進めると、法的にも損をするケースがあります。
6. 行政書士ができるサポート
行政書士は、相続関係の書類作成や、遺言書の作成支援を通じて、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしています。 具体的には、遺言内容の整理・遺留分への配慮・相続関係説明図や財産目録の作成など、手続きの最初の段階からご相談を受けられます。
また、「すでに争いになってしまった」という方にも、家庭裁判所への提出書類の作成補助など、法的サポートの橋渡しを行うことが可能です。 専門家に相談することで、冷静な判断と円満な解決へと近づけるケースは多くあります。
7. まとめ:遺留分を理解して“もめない相続”を
「遺言で全部あげる」は、残された家族に思わぬ火種を残すことがあります。 しかし、遺留分を理解し、正しく対応すれば、争いは防げます。 遺言は「残す人の意思」であると同時に、「残される人への思いやり」でもあります。 今のうちに整理しておくことで、あなたの想いを穏やかに未来へつなぐことができます。
行政書士として、私は相続の“もめない仕組みづくり”をお手伝いしています。 遺留分の考え方や遺言内容のご相談など、お気軽にご相談ください。 小さな不安のうちに行動することが、いちばん大きな安心につながります。
クイズ
読み込み中…
…
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。