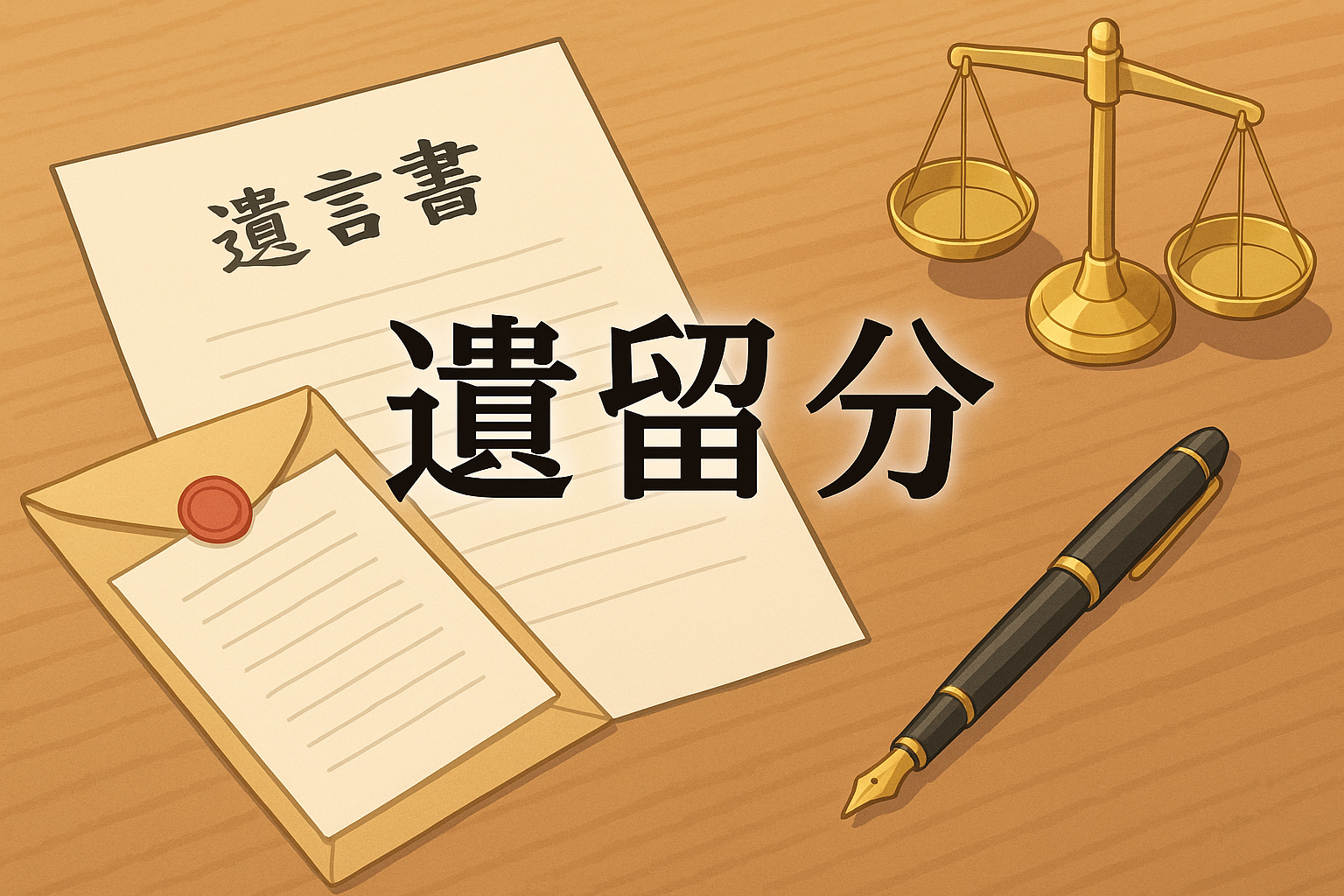「たとえ家族でも、相続できないことがあるの?」──そう驚かれる方も多いでしょう。 実は、法律では一定の事情がある場合に、相続人から外される制度が存在します。 それが「相続欠格(けっかく)」と「相続廃除(はいじょ)」です。 本記事では、これらの違いや具体的なケース、手続きの流れを行政書士の視点でわかりやすく解説します。
1. そもそも「相続欠格」と「相続廃除」の違いとは?
どちらも「相続権を失う」制度ですが、その理由と手続きには大きな違いがあります。
相続欠格とは?
相続欠格とは、本人の行為によって当然に相続権を失うことをいいます。 つまり、家庭裁判所の判断を待たず、法律上自動的に相続人ではなくなるのです。
欠格の理由は、主に次のような「極めて悪質な行為」があった場合に限られます。
- 被相続人(亡くなった人)を故意に殺した、または殺そうとした
- 他の相続人を殺した、または殺そうとした
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
- 詐欺や強迫によって遺言を妨げた、または取り消させた
たとえば、親を殺害してしまった子どもは当然に相続人から外されます。 これは社会的な倫理を守るための制度であり、「自動的に相続できなくなる」という点が最大の特徴です。
相続廃除とは?
相続廃除は、欠格と違い家庭裁判所の手続きによって相続権を取り消す制度です。 廃除の対象は主に「著しい非行がある推定相続人」で、たとえば次のようなケースが該当します。
- 被相続人(親など)に対して暴力や暴言を繰り返した
- 著しい侮辱行為を行った(人格を否定するような言動など)
- 生活費を渡さず放置した、扶養義務を果たさなかった
欠格が「犯罪行為」で自動的に相続権を失うのに対し、廃除は「人間関係上の深い対立」による手続き的な除外です。 したがって、廃除を行うためには家庭裁判所に正式な申立てが必要になります。
2. 相続欠格の具体的な事例
たとえば、親の遺言書を勝手に破いたり、書き換えた場合は「遺言書の偽造・破棄」にあたります。 これは法律で明確に相続欠格事由とされています。 また、「他の相続人を殺そうとした」だけでも未遂で欠格になることがあります。
欠格はあくまで法律上の自動効果であり、裁判を待つ必要はありません。 ただし、実際に欠格に該当するかどうかは、争いになった場合には家庭裁判所が判断します。
3. 相続廃除の手続きの流れ
① 廃除の申立て
被相続人本人が生前に「この子には財産を渡したくない」と感じた場合、家庭裁判所に廃除の申立てを行います。 被相続人の死亡後に行う場合は、遺言で「廃除を望む」旨を明記し、遺言執行者が申立てをします。
② 家庭裁判所の審理
裁判所は、廃除の理由が正当かどうかを慎重に審査します。 たとえば暴言や暴力の記録、医師の診断書、第三者の証言など、具体的な証拠が求められます。
③ 審判・通知
廃除が認められると、その相続人は正式に相続権を失います。 ただし、この決定に不服がある場合は、本人から不服申立て(即時抗告)も可能です。
廃除は被相続人の「強い意思」を尊重する制度である一方、誤用されると深刻な家族トラブルを招くため、慎重に判断されます。
4. 廃除後に関係を修復した場合「取消し」も可能
興味深いのは、廃除は「取り消す」こともできる点です。 たとえば、過去に不仲で廃除を申立てたものの、その後に和解し関係が回復した場合、被相続人は廃除の取消しを申し立てることができます。
また、遺言書で「以前の廃除を取り消す」と記載すれば、その時点で廃除は無効になります。 つまり、廃除は最終的な絶縁ではなく、「関係修復の余地が残る制度」でもあるのです。
5. 欠格・廃除と代襲相続の関係
欠格や廃除によって相続人が除かれた場合、その人の子ども(孫世代)はどうなるのでしょうか? 実は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって孫が代わりに相続できます。 兄弟姉妹の欠格では、その子ども(甥・姪)にまで代襲相続ができます。
このように、欠格・廃除の効果は本人だけに限定される点も押さえておきましょう。 (参考:相続放棄は、そもそも最初から相続権がなかったこととして取り扱われるため、代襲相続はありません。)
6. 家族トラブルを防ぐためにできること
欠格や廃除の制度は、「最終手段」といえます。 家族間の関係が深くこじれた結果、やむを得ず選択されることが多いのです。 だからこそ、廃除に至る前の話し合いや遺言書での意思表示がとても重要になります。
行政書士としての経験から言えば、「相続トラブルの多くは、準備不足と誤解から生まれる」と感じます。 相続関係を整理するエンディングノートや、遺言書の作成支援を受けることで、家族間の衝突を未然に防ぐことができます。
7. まとめ:欠格・廃除を理解して“争わない相続”を
相続の欠格や廃除は、誰にでも起こり得る「相続権の例外」です。 身内であっても、法律上の理由や手続きによって相続できなくなることがあります。
一方で、それは「家族の断絶」を意味するものではなく、信頼関係を守るための制度でもあります。 感情的に動く前に、法律の仕組みを理解し、冷静に判断することが大切です。
行政書士は、廃除申立書や遺言書の作成支援を通じて、相続の準備からトラブル防止まで幅広くサポートしています。 不安や疑問を感じたら、まずは専門家に相談してみてください。 「知ること」から、安心できる相続が始まります。
クイズ:欠格・廃除の基礎
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。