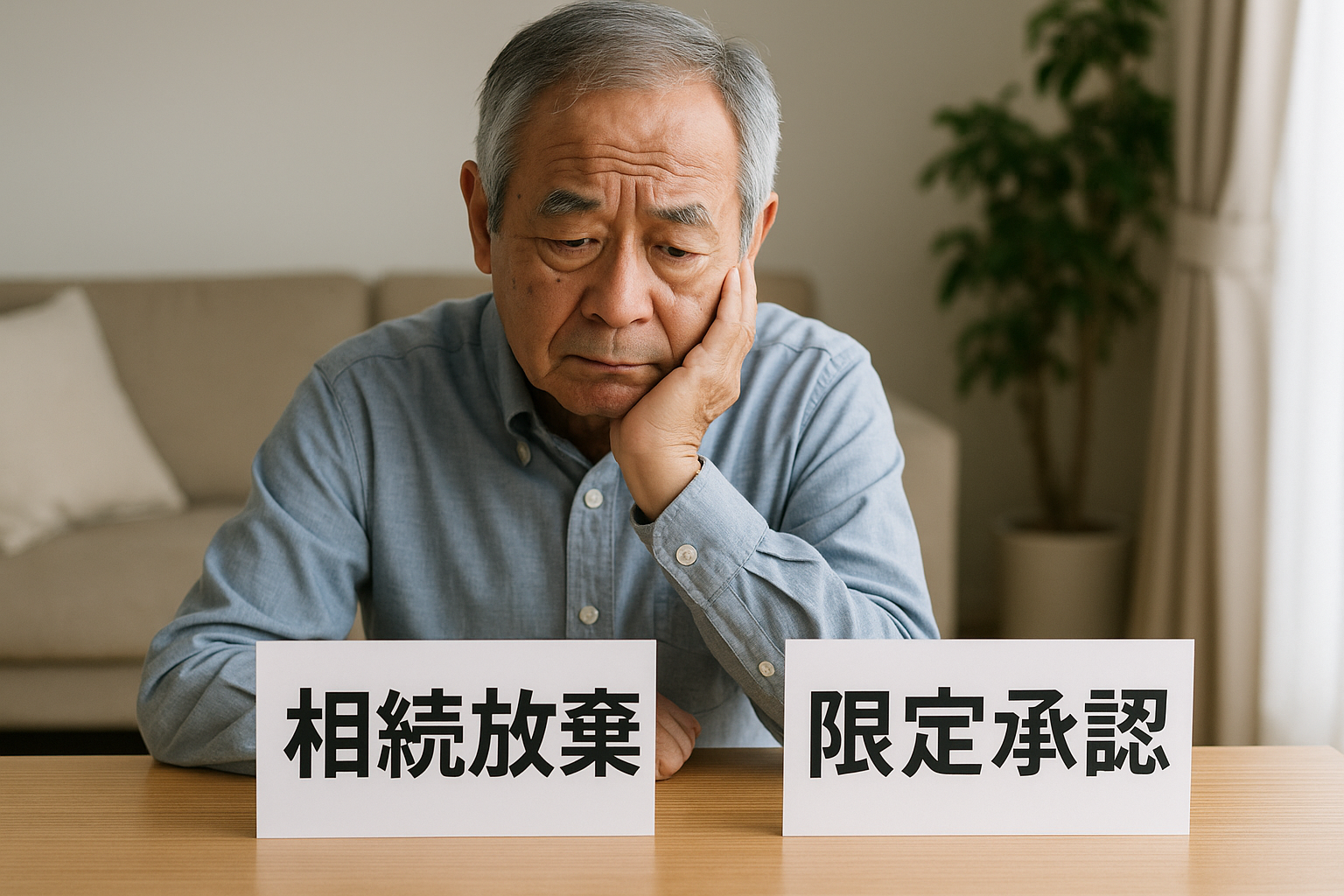都市部に農地をお持ちの方から、「うちの土地が『生産緑地』に指定されているけど、何なのかよくわからない」というご相談をよくいただきます。生産緑地とは、都市の中に残された農地を守るために設けられた制度です。指定を受けると税金の優遇がある一方で、売却や転用には大きな制限がかかります。
この記事では、行政書士が、生産緑地の仕組み・メリット・デメリット・税金・相続・解除手続きなどを、専門知識がなくても理解できるように丁寧に解説します。
1. 生産緑地とは?都市部の「農地を守る制度」
生産緑地とは、「市街化区域内にある農地のうち、一定の条件を満たすものを、農地として保全するために指定された土地」のことです。これは1992年の「生産緑地法改正」によって始まった制度で、都市化が進む中でも緑や農業を残すことを目的としています。
たとえば東京や大阪などの住宅街の中にぽつんと残る田畑――これが生産緑地であることが多いです。指定を受けると、原則として農地として利用し続ける義務が生じ、宅地や駐車場などに転用することはできません。
生産緑地は「農地を守る代わりに、税金の優遇を受けられる制度」。ただし、自由に売却や転用ができない点が大きな特徴です。
2. 生産緑地の指定条件と指定を受けるまでの流れ
生産緑地に指定されるには、次の条件を満たす必要があります。
- 市街化区域内にあること
- 500㎡以上の面積があること
- 農業用水・排水などの基盤が整備されていること
- 今後も農業を継続できること
指定を希望する場合は、市町村への申請後、農業委員会の意見を経て知事(または市長)が指定します。指定を受けると「生産緑地地区」として都市計画に位置づけられ、固定資産税などが大幅に軽減されます。
3. 生産緑地のメリット:固定資産税が大幅に軽減される
生産緑地の最大のメリットは税金の優遇です。通常、市街化区域内の土地は宅地並み課税が適用され、固定資産税や都市計画税が非常に高額になります。
しかし、生産緑地に指定されると、農地としての評価額で課税されるため、固定資産税はおおよそ100分の1程度に抑えられます。たとえば、宅地並み課税で年間30万円かかる土地でも、生産緑地に指定されることで数千円〜数万円程度になるケースもあります。
また、相続税においても「小規模宅地等の特例」などが適用されやすく、農業を続ける限りは税負担を大きく抑えられる点が大きな利点です。
税金の優遇=土地を維持しやすくなる仕組み
都市化が進む中でも、農業を続ける人にとっては非常にありがたい制度です。
4. デメリット:売却や転用に厳しい制限がある
生産緑地のデメリットは、自由に売れない・使えないことです。指定を受けた土地は原則として農業以外の用途に転用できません。
また、所有者が「もう農業を続けられない」となっても、すぐに自由売却できるわけではありません。まず市町村長に「買取りの申し出」を行い、自治体や農業関係者が買い取らない場合に初めて、自由に売却できるようになります。
さらに、生産緑地に指定された土地を勝手に駐車場や資材置場にすると、農地法・都市計画法違反に問われることがあります。
2022年問題とは?
1992年に指定された生産緑地の多くが、30年の指定期間満了を迎えるのが2022年でした。これをきっかけに、解除や売却が相次ぐのではないかと注目されました。実際には、市町村が再指定を進めるなどして一気に売却が進む事態は避けられましたが、今後も「世代交代」「相続」などを契機に、解除の相談は増えています。
5. 生産緑地を解除するには?「買取り申出」と「農地法の許可」
生産緑地を解除するには、次の手順が必要です。
- 買取り申出:農業を続けられない場合、市町村長に「買い取ってほしい」と申し出ます。
- 買い取り対象者の確認:自治体や農業団体が買い取らない場合、はじめて制限が解除されます。
- 農地法の手続き:解除後に宅地などへ転用する場合は、農地法第4条・第5条の許可が必要です。
つまり、解除には「市町村+農業委員会+農地法」の3段階のハードルがあります。申請に必要な書類や期間も長く、専門家のサポートがあるとスムーズです。
※但し、解除の条件としては、指定から30年経過や主たる農業従事者の死亡等に該当する場合です。
6. 相続と生産緑地の関係
相続の際、生産緑地は「農地」としての価値で評価されるため、相続税の負担は軽くなります。ただし、相続人が農業を続ける意思がない場合は、生産緑地の維持が難しくなることもあります。
この場合は、相続前に「今後どうするか」を家族で話し合い、場合によっては解除申請を検討する必要があります。行政書士など専門家に相談することで、相続・税金・手続きを総合的に整理できます。
7. 生産緑地制度の今後と2022年以降の動向
2022年以降、自治体によっては「特定生産緑地」という新たな仕組みを導入しています。これは、従来の30年縛りを延長し、引き続き税制優遇を受けながら農地を維持できる制度です。
今後も都市部では「緑の保全」と「土地の有効活用」の両立が求められ、柔軟な制度運用が続く見通しです。所有者としては、「農業を続けるのか」「解除して活用するのか」を早めに検討しておくことが大切です。
8. まとめ:生産緑地は「守るか・活かすか」を考える時代へ
生産緑地は、税金面で非常に有利な制度ですが、その代わりに使い道が制限されるという側面があります。固定資産税を安く抑えたい場合には大きなメリットですが、将来的に売却や転用を考えている場合は計画的な対応が必要です。
特に、相続をきっかけに「農業を続ける人がいない」というケースは増えています。そうしたときこそ、制度を正しく理解し、行政書士など専門家に相談することで、最適な判断ができます。
クイズ:生産緑地の基礎
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。