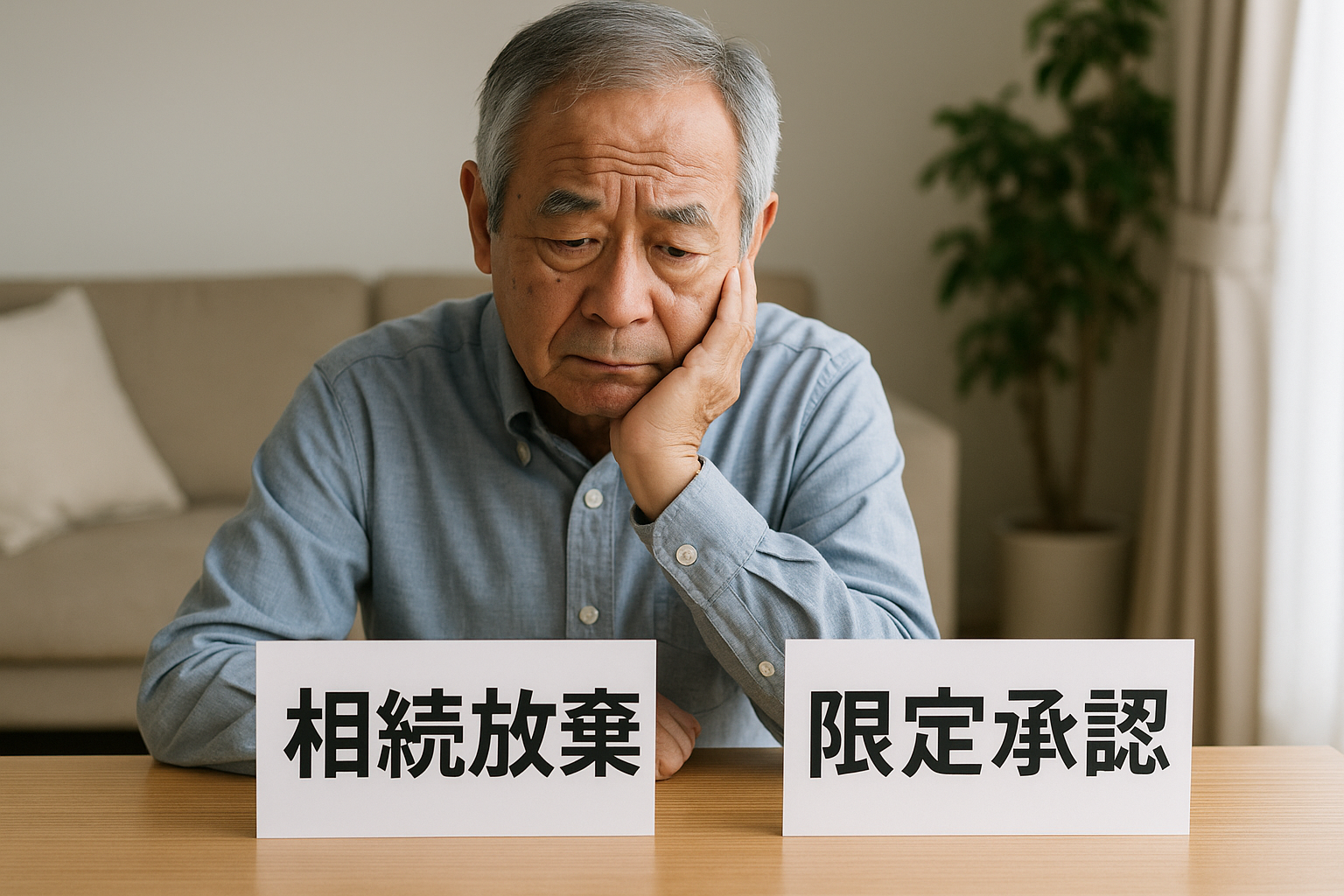「相続のたびに戸籍を何通も集めて、あちこちに提出するのが大変だった」―― そんな声を背景に誕生したのが法定相続情報一覧図という制度です。 これは、複雑な戸籍の束を1枚の図にまとめ、法務局が内容を確認してくれる「相続関係の証明書」のようなもの。 相続登記や銀行の名義変更など、さまざまな手続きをぐっと楽にしてくれます。 今回は、制度の概要やメリットを分かりやすく紹介します。
1. どうして「法定相続情報一覧図」が注目されているの?
相続登記の義務化が始まり、全国で「どうやって手続きを進めたらいいの?」という声が増えています。 相続は、家族にとって大切な節目である一方で、戸籍集めや書類の整理など、想像以上に手間のかかる作業です。 特に、被相続人(亡くなった方)の戸籍は「出生から死亡まで」の連続が必要で、 転籍や改製が多い場合には、複数の市町村から取り寄せなければなりません。 そんな中で、戸籍の束を1枚にまとめる仕組みとして誕生したのが「法定相続情報一覧図」です。
これは国(法務局)が提供する制度で、無料で利用できます。 戸籍一式を提出して内容を確認してもらうと、 被相続人と相続人の関係をまとめた図(=一覧図)に認証印が押されて交付されるのです。 いわば「法務局お墨付きの家系図」のようなもので、 これを銀行や保険会社などに提示すれば、戸籍の束を何十枚も提出しなくても済むようになります。
2. どんなときに役立つの?
一覧図があると、相続登記のほかにも、銀行預金の解約、証券の名義変更、保険金の請求などで活用できます。 手続きごとに同じ戸籍を何度も出す必要がなくなるため、 「あの書類、どこに出したっけ…?」と戸惑うことも減ります。 また、複数の相続人がいる場合でも、同じ図を共有して確認できるため、 家族間での話し合いにも役立ちます。
さらに嬉しいのは、何部でも無料で交付してもらえること。 たとえば、銀行用・不動産登記用・保険用と分けて用意しておけば、 スムーズに各手続きを進められるようになります。
3. どんな情報が載っているの?
一覧図には、被相続人の氏名や生年月日、死亡日、住所、 そして相続人一人ひとりの氏名・続柄などが記載されます。 財産の内容や金額は載りませんが、「誰が相続人なのか」を明確にする点で非常に有効です。 つまり、財産の内訳を知るためのものではなく、 相続人を確定させるための資料だと考えるとわかりやすいでしょう。
※相続放棄や代襲相続など、少し複雑な事情がある場合は、 一覧図の作成時に注意が必要です。専門家に一度確認してもらうと安心です。
4. 実際に作るのは大変?
制度自体は無料で、だれでも申し込むことができます。 ただし、被相続人の戸籍をすべて集め、相続人全員の関係を正確に整理する作業は、 慣れていない方には少し難しいかもしれません。 戸籍の読み方や「どの市区町村に請求するか」は、思った以上に複雑です。 特に明治・大正時代の戸籍や改製原戸籍(かいせいげんこせき)は、 手書きのくずし字で記載されていることもあり、専門家でも慎重に確認する部分です。
また、一見正しくつながっているように見えても、 ひとつの抜けや記載ミスで「一覧図が受理されない」というケースもあります。 そのため、行政書士などに依頼して、最初から正確な書類を整えてもらう方も増えています。
5. 専門家に依頼するメリット
① 戸籍収集と整理を一任できる
行政書士などの専門家は、どの市区町村からどの戸籍を取ればよいか、 どのように読み解いて整理すれば一覧図が成立するかを熟知しています。 ご自身で何週間もかかる作業が、専門家に頼むことでスムーズに完了することも多いのです。
② 間違いのない図面を作成してもらえる
一覧図は「誰が相続人か」を法的に示す重要書類。 間違いがあると、相続登記や銀行の手続きがすべてやり直しになることもあります。 行政書士が作成すれば、法務局の確認基準を踏まえた正確なものを提出でき、 補正(やり直し)を防ぐことができます。
③ その後の手続きまで見通してもらえる
法定相続情報一覧図は、あくまで「スタート地点」にすぎません。 実際には、遺産分割協議書の作成、不動産登記、銀行手続きなど、次の段階が続きます。 行政書士であれば、他士業(司法書士・税理士など)と連携して、 一連の流れを整理しながら、最短ルートで進める提案が可能です。
6. 一覧図を活用することで得られる安心感
この制度をうまく活用すれば、面倒だった相続の手続きがぐっと分かりやすくなり、 ご家族の心理的な負担も軽くなります。 「もう少し元気なうちに、家族のために戸籍関係を整理しておこう」 「もしもの時に、子どもたちが困らないように」 そんな思いを形にするのにも役立つのが、この一覧図なのです。
行政書士としても、これをきっかけに相続全体の見通しを整理し、 どんな財産があり、誰がどんな形で引き継ぐのかを早めに考えておくことをおすすめしています。 将来の相続を“争続”にしないためにも、 法定相続情報一覧図の作成は「第一歩」としてとても有効です。
7. まとめ:手続きを軽くし、家族の安心を残すために
法定相続情報一覧図は、相続の「面倒」を減らすための心強い味方です。 無料で使える制度ですが、正確に作るためには専門的な知識と丁寧な確認が欠かせません。 ご自身で手続きを始める前に、ぜひ一度、行政書士などの専門家にご相談ください。
戸籍の整理から相続関係説明図の作成、そして一覧図の申出まで、 専門家が伴走することで、時間も心の余裕も生まれます。 あなたとご家族が安心して次のステップへ進めるよう、私たちがお手伝いします。
クイズ:法定相続情報一覧図の基礎
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。