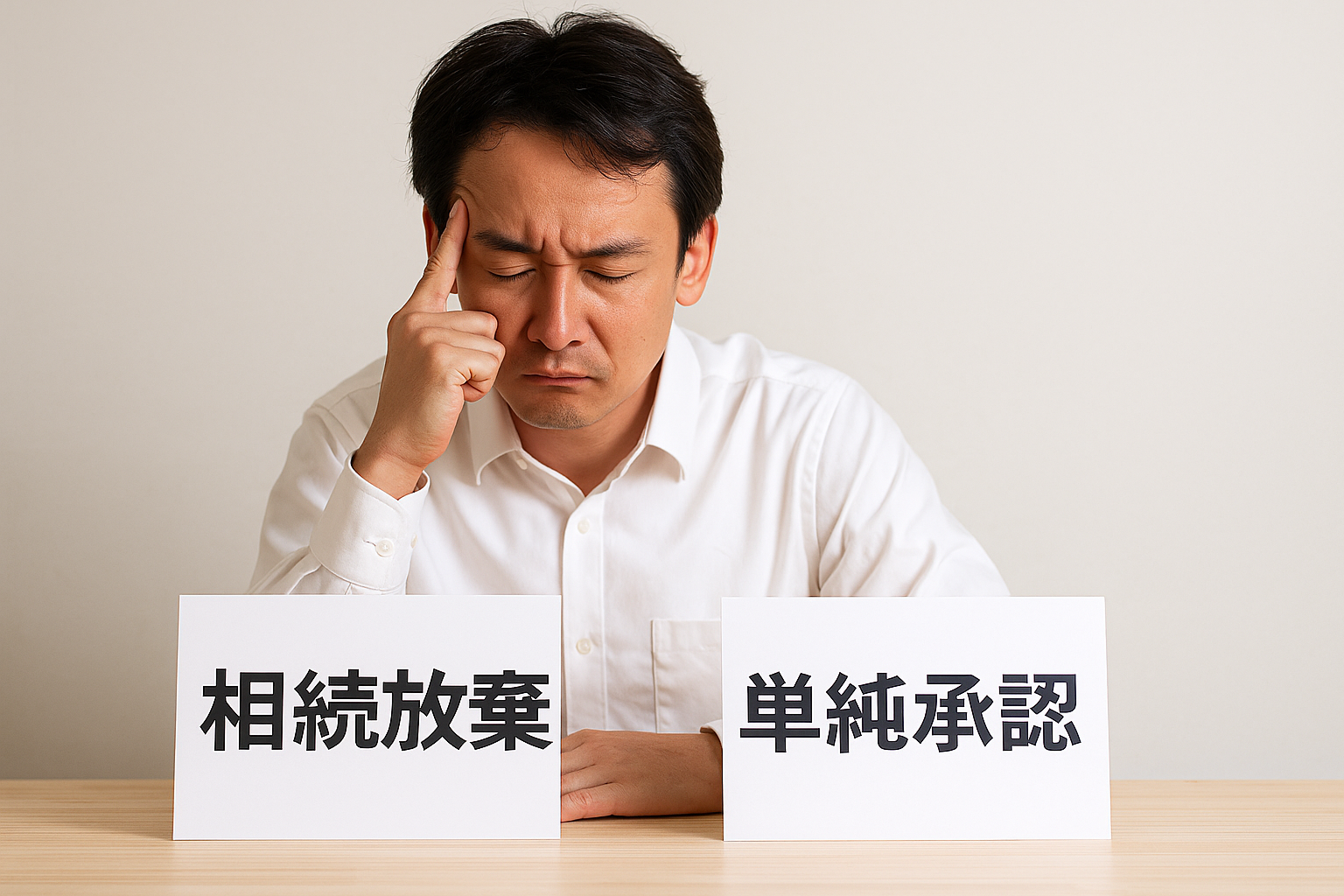1. はじめに
「農業をやめた」「もう体力的に畑を維持できない」 そんな理由で、農地をそのままにして放置している所有者の方は少なくありません。ですが、農地を使わずに放置することにはさまざまなリスクが潜んでいます。
この記事では、農地を放置したらどうなるのか、どんな不利益があるか、そしてその対処法をわかりやすく解説します。特に「遊休農地と判断される」「固定資産税の増加」「近隣トラブル」「土地の価値低下」「活用方法」「専門家の活用」など、現実的に押さえておきたいポイントを中心に紹介します。
2. 放置された農地は「遊休農地」とみなされる可能性
長期間使われていない農地は、農業委員会が現地調査を行うなどして「遊休農地」と判断されることがあります。遊休農地とは、名目上は農地であっても、実際には耕作や利用がされていない土地のことをいいます。
遊休農地に指定されると、行政から利用改善の指示が出されるケースがあります。たとえば「草刈りをしてください」「作物を作るようにしてください」などの勧告です。一定期間改善が見られない場合には、土地所有者に対して強制的な措置をとられる可能性も完全には否定できません。こうした制度は、土地が荒れたままで地域環境を悪化させたり、地域の農地ネットワークを阻害したりすることを防ぐために設けられています。
3. 放置農地で起こりうる生活・環境トラブル
農地を放置すると、雑草が急激に繁茂するのは自然な流れです。その草が隣地に侵入したり、害虫・小動物の巣になったりして、近隣住民への迷惑が発生することはよくあります。特に夏場は雑草の勢いが強く、刈りきれないほどになることも。
さらに、不法投棄が行われやすい環境にもなります。誰も見ていない土地にゴミを捨てるケースはよくあり、ごみ処理のコストや周囲の景観悪化、衛生上の問題が生じることがあります。こうした状態が続けば、近隣から苦情を受けたり、地域との信頼関係にヒビが入ったりすることもあります。農地を放置することは、土地所有者自身だけの問題にとどまらず、地域とのつながりにも影響し得る行為なのです。
4. 遊休農地指定と「固定資産税増税」の可能性
特に重要な点として、遊休農地に指定されると固定資産税が上がる可能性があります。というのも、農地は「農地価格相当額」によって税額が抑えられて課税されている場合が多く、耕作されている状態を前提にした軽減措置が適用されているケースがあります。
一方で、農地が遊休状態と判断されると「農地としての利用が見込めない土地」として、軽減措置が剥がされ、評価方式が変わることがあります。結果として、税負担が大きくなるリスクが生じます。地域・自治体によって運用が異なるため、一律ではありませんが、遊休農地指定と税制面のリスクは見逃せないポイントです。
この点を知らずに長く放置していると、気づいたときには高い税負担を強いられることになるので、注意が必要です。
5. 放置すると土地の価値も落ちる
一度荒れた農地を元に戻すには、草刈り・除根・整地・土壌改善など多くの手間と費用がかかります。こうした復旧コストを買い手が見積もると、土地の価値は目に見えて下がります。
また、「遊休農地」に指定されている記録が残っていれば、買い手・融資機関からは「管理不良な土地」と見られやすく、結果的に価格交渉で大幅に値引かれてしまうこともあります。つまり、放置=価値低下という構図が成立することが多いのです。
6. 放置を避けるための活用方法
農業を続けられない事情があるなら、放置ではなく以下のような活用方法を検討するとよいでしょう:
⑴貸し出す
近隣の農家や既存の担い手に土地を貸して耕作してもらう。定期的な収入源にもなります。
⑵農地中間管理機構を利用する
公的機関を通じて利用者をあっせんしてもらう方法。比較的手続きが整っており安心感があります。
⑶転用を検討する
駐車場や宅地用途に変える「農地転用」の可能性があれば、それを進めてから売却または活用する。
⑷自主管理をする
草刈りや定期的な見回り、周囲への配慮を維持し、不法投棄や雑草侵入を防ぐ。
重要なのは、「何もしないこと」を選ぶのではなく、少しずつでも「使う/貸す/管理する」アプローチを検討することです。
7. 専門家に相談することで安心を得る
農地の管理や活用には、法令や地域条例、税務面など複数の知識領域が関わります。どの活用方法が選べるか、どの許可・届出が必要か、税制上の扱いはどうなるか。こうした判断は専門家の視点が非常に役立ちます。
行政書士、土地家屋調査士、税理士などと連携して相談できれば、無駄なコストを減らしながら、将来につながる土地管理が可能です。特に「遊休農地指定」「税制リスク」を回避して、安心して所有できる形に整えるためにも、早めに専門家に声をかけておくことをおすすめします。
8. まとめ
農地を使わずに放置すれば、まず「遊休農地」に指定される恐れがあります。その結果、行政からの勧告・強制措置、不法投棄や雑草問題、土地の価値低下、そして固定資産税の増加といったさまざまなリスクが生じます。
ですが、「使わないから手放す」のではなく、「適切に管理する」「貸す」「転用する」などの方法をとることで、多くのリスクを防ぎ、土地を無駄にしない選択肢が残ります。迷ったときはぜひ専門家に相談し、大切な土地を安心して次世代へつなぎましょう。
【事務所概要】
行政書士やまだ法務事務所
代表者:山田 勉
所在地:奈良県生駒郡平群町光ヶ丘1丁目3番5号 (ご来所は、全予約制です。)
電 話:0745-45-6609 (受付時間 午前9時~午後5時)
F A X : 同 上 (24時間受付)
メール :お問い合わせ
休業日:土日・祝日・年末年始 ※予めご連絡いただければ休日対応いたします。
対象地域:奈良県、大阪府、京都府 ※ZOOM面談やご自宅への訪問をいたします。